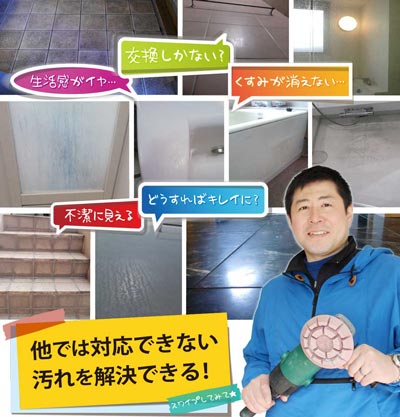硬度0(ゼロ)の軟水とは?
- 水1000ml中に溶けているカルシウムとマグネシウムの量を表わした数値を「硬度」といいます。
- 例えば80mg/L(1リットルあたり80mgのカルシウムが溶けている)は「硬度80」と表します。
- 硬度0の軟水とは、Ca/Mgの量を計る硬度試薬で「0」値になる水です。
- つまり、カルシウムとマグネシウムを「全く含まない」水です。
洗う 専用の水
- 水を「飲む」「洗う」の用途に分けて考えます。
- 硬度0の軟水は、飲料用の水とは別のカテゴリです。
- ミネラルは体に必要(栄養素として)。しかし「洗う」用途には不要です。
- 水は、あらゆる物質を溶かし込むことができる「溶剤」です。
- 水に「汚れ」や「何らかの有効成分」取り込ませたい時に、金属(ミネラル)イオンが既に溶け込んでいると、邪魔です。
- ミネラルを事前に取り除いた水で洗うと、溶剤としての機能が向上します。
身近にある「硬度0」の水
- ボイラー。タンク・配管内部を水垢が覆うと、熱効率が下がります。軟水化は、動力&発電システムの効率を上げるのに役立ちます。
- 窓洗浄システム。水道水を純水に変換し、窓ガラスを洗います。そのまま乾いても水滴の跡が残らないので、高層・足場が無い現場に有効です。
- 洗車場、銭湯など…水道水を硬度0に変換しているところ、たまにあります。
日本の水道水とは
- 日本の水道水は、全て「ミネラルウォーター」。

山に降った雨が土に染み込んで→

土中に染みた水が時間を経て湧き水になって→

集まって川になって→

水源になる。
- つまり、日本の水道水は「いったん地下に潜ったことがある」水。
- 地下の成分(ミネラル)を必ず溶かし込んでいるのです。
- 火山がある(富士山を含む)エリアは、地質をそのまま写し取る形で、硬度高め。
- ちなみに、雨水は全て「硬度0」です。(大気汚染由来の金属は除く)
 補足:「雪解け水」と硬度
補足:「雪解け水」と硬度
冬の山は凍る。雪が溶けない。地上に水が貯蔵されるので、水の供給が減る時期です。硬度が薄まらず、水が硬くなる時期でもあります。
私が暮らす横浜市北部で水道水の硬度を計りますと、冬季は70~75、その他の季節は50~60でした。
冬の肌荒れは、空気の乾燥だけでなく、水道水の硬度上昇も一因かと思います。
春先以降、硬度0の雪解け水が一気にダムに注ぎ込みます。硬度もやわらぎます。そして梅雨、さらに雨水が流入。肌の塩梅も上々に。
「北海道の水は軟らかい」ってよく聞きます。雪解け水の量がとても多いからです。
- 雪解け水で希釈されない地下水源エリアは、硬度が高いです。武蔵野市、三鷹市、座間市など。
- 雪がいっぱい積もるような山が近くに見当たらない南房総なども、硬度が高いです。
 補足:「カルキ」と硬度
補足:「カルキ」と硬度
「水垢は、カルキが原因」、「人間が不自然な形で手を加えているから、変になるんだ」とお考えの方が多いように思います。
浄水場の水は原則「飲料用」なので、消毒するといっても化学物質を多量に入れられません。そして、基準値(飲めないレベル)以下のミネラルは原則ノータッチです。
以下例の白いカリカリ汚れは、人間が加えた化学物質というよりも、もともと自然の中にあったミネラルとお考えください。
「日本は軟水の国」だからトラブル無しじゃないの?
- 日本の水道水質基準は、300mg/L以下。日本では、それ以上の硬度は日常生活に無いということです。
- 硬度120未満が軟水/120以上が硬水 と世界を2分するならば、日本は軟水の国といえます。
- しかし日本には、通年30~40の地域もあれば、100超の地域もあります。
- 「日本は分類上軟水の国」と「硬度トラブル無く過ごせる」は、切り離して考えてみてください。
- 今まさに硬度トラブルを感知している人からすると「日本=軟水=気にすることはない」と言い切るのは、酷なことだと思います。
 補足:君が代の「さざれ石」
補足:君が代の「さざれ石」
さざれ石の巌となりて、苔のむすまで。細かな石が成長し大岩になって、苔が生えるまで…という意味です。
さざれ石は、大きな神社で見られます。写真は、鶴岡八幡宮のさざれ石。
水に溶けたミネラルが小石の隙間を埋め、くっついて大きな塊になる。日本の水には、ミネラルがバッチリ溶けているのです。
ミネラル入りの水で洗うと、こうなります
石けんカス ソープスカム 金属石鹸
- 洗面器でタオルをすすぐと、ブワッと白く浮いてくる。それ、垢ではなくて石けんカスです。
- 不溶性(水に溶けない)。
- 白っぽく、厚ぼったい。
- 濡れるとベタベタしている。
- 乾くとパサパサしている。
- 酸化した脂っこい臭いがある。
- 栄養豊富 → カビが好む。
- 水を弾く。
- 石鹸や人から出た汚れが付着しやすい「腰より下」の位置で多く見られる。

浴槽のエプロンカバー。洗い場からの跳ね返りが多くかかる。

浴室床。座る位置を取り囲むように付着しています。

浴室扉の内側。すすいだ水が当たりやすい箇所。
石鹸の泡が付いちゃった。シャワーで流そう。
石鹸を付けて洗って、水ですすごう。
その瞬間、もう出来ている…
それが「石けんカス」なのです~(ノ´□`)ノ
 補足:石けん水は白く濁る
補足:石けん水は白く濁る
石けんを水道水で溶かすと、水溶液は白濁します。
溶けるやいなや石鹸カスが生成されるため、溶液は透明にはなりません。
ペットボトルで実験してみてください。振っても振っても溶けない白。しばらく置くと、水面あたりに垢のようなものがくっついて。
そして、かなりの量を溶かさないと泡が出来ない。
泡立てて石けんの界面活性作用を発揮させるには、今ある水道水中のミネラルを全て反応させてから「追い石けん」が必要。これが「石けん、すぐ減る」の理由です。
一方、こちらは、固形石鹸を硬度0の軟水に入れて溶かした写真です。透明の石けんだからじゃない?いえいえ、普通のマルセイユ石けんです。
石けんカスが生成されないと、石けん溶液はクリアです。そして、少量でも泡立つ!
水垢 スケール うろこ
- 水道水に含まれるミネラルが、干上がって出来た痕跡。
- くすみ・濁り・くもりとして、素材本来の質感を損ねる。
- しずく(ウロコ)状やモヤモヤ(まだら)として目視できる。
- 乾くと白く目立つ。
- 濡れると、あんまり目立たない。
- 浴室用洗剤や漂白剤を塗っても、変化が見られない。
- ブラシやスポンジで擦っても落ちない。硬い。
- 人の汚れというよりも、水道水のみが残る位置で多く見られる。

浴室鏡とカウンター。

湯沸し器のスイッチパネル。

壁面パネル。
シャワーを掛けて、全体を浄めよう。
水だけで汚れを洗い流そう。
その積み重ねで出来る…それが水垢ですヽ(;´Д`)ノ
したがって、水で濡らした後に布やスクイジーを使って徹底的に水分を除けば、水垢は予防できます。濡らしたまま自然乾燥 → 水垢 と覚えておいてください~。
 補足:シリカスケール
補足:シリカスケール
軟水器を通したカルシウムとマグネシウムを全く含まない硬度0の水にも、シリカは溶けて含んでいます。
シリカは、ガラスの原料。硬くて透明、とイメージすると良いです。水に濡れると消える、乾くと白く見えてくる。そんな薄~い摺りガラスのような水垢になります。ユニットバスの樹脂パネルよりも固いので、いったん付くとクリーニングは至難です。
しかし、軟水器を使ってカサ高い(かつ量も多い)分子であるCa/Mgを除去すれば、表面に付着する凹凸が減り、シリカの足場は失われますので、シリカスケールも少なくなったと感じることができるかと思います。
シリカも含めて除去できるシステムもありますが、「日常生活で・一般的な住宅で」となると高価で効率も悪く、現実的に難しいのが実情です。
 補足:キレート
補足:キレート
ほとんどの方がお掃除で洗剤を使うことにご不便を感じていらっしゃらないかと思います。
市販の洗剤には、Ph(酸・アルカリ)を傾けるための成分や界面活性剤の他、ミネラルを含む水道水で使っても問題が出ないよう水軟化剤・金属封鎖剤といった添加物が入っています。
金属石鹸になる前に、水道水に溶け込んでいる金属(カルシウムやマグネシウム)をいち早くパクっと封じることができれば、洗浄成分は無駄にならず効果を最大限に発揮することができます。
お風呂掃除用洗剤など金属石鹸が発生しやすい場所で使う洗剤には、キレート剤は多めに添加されています。
「大理石の浴室で、市販の浴室掃除用洗剤を使っていた。中性洗剤だから安心していたが、大理石が次第にくすみ光沢感が失われた。」というトラブルは、大理石のカルシウムと結合しまくってしまったキレート剤の仕業と言えます。